首の症状について
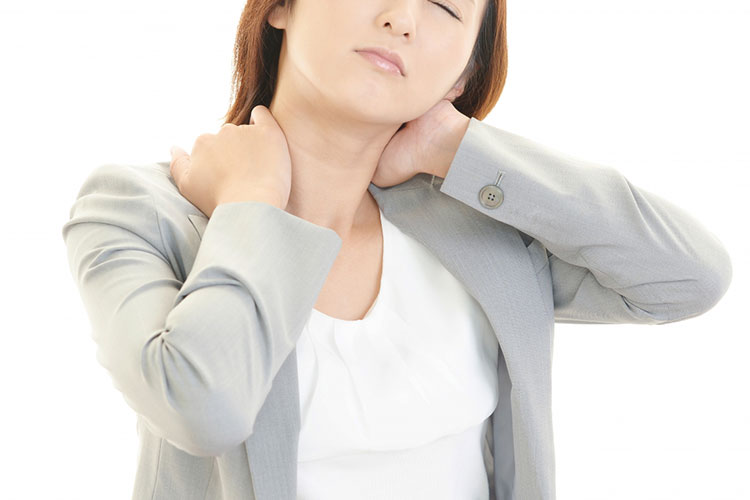
頚部痛
頚部痛は首の痛み全般を指すもので、首の後ろの筋肉が過度に緊張したり、骨や関節、神経などが障害されたりすることで、首に痛みや不快感が生じる状態です。痛みが肩、背中、腕、指先などに広がったり、頭痛、吐き気、めまい、しびれなどの症状を伴ったりすることもあります。
頚部痛を引き起こす原因は様々ですが、大きく分けて、筋肉や関節の問題と神経の問題の二つがあります。筋肉や関節が原因の場合は、姿勢の悪さや長時間のデスクワーク、運動不足、ストレス、睡眠不足、寝具との相性が悪いこと、更年期障害の影響などが挙げられます。一方、神経が原因の場合は、頚椎椎間板ヘルニア、頚椎症、靱帯骨化症などの疾患であることが考えられます。これらのほか、交通事故によるむち打ちなどの外傷、腫瘍、関節リウマチなどの炎症性疾患も頚部痛の原因となります。
頚部痛の治療法は、その原因や症状の程度によって異なります。軽度の場合は、日常生活や仕事での姿勢を正す、ストレッチやマッサージなどのセルフケアをする、湿布や痛み止めなどを用いるといったことで改善する場合もありますが、痛みが強い場合や、しびれや麻痺などの神経症状を伴う場合は一度ご受診ください。
治療にあたっては、レントゲン検査やMRI検査などを行い、原因を特定した上で、適切な治療を行っていきます。治療法には、薬物療法、運動療法や物理療法、装具療法などのリハビリテーション、神経ブロック注射、手術などがあります。頚部痛を予防するためには、日頃から正しい姿勢を心掛け、適度な運動、バランスの取れた食事、十分な睡眠を摂ることが大切です。また、長時間同じ姿勢での作業を避ける、こまめな休憩を取る、ストレッチなどで首や肩の筋肉をほぐすなどの対策も有効です。
頚椎椎間板ヘルニア
頚椎椎間板ヘルニアは、首の骨と骨の間にあってクッションの役割を果たす椎間板が、変形したり飛び出したりすることで、近くの神経を圧迫し、痛みやしびれ、肩こりなどの症状を引き起こす病気です。
変形の原因としては、主に、加齢、スポーツなどによる外傷、長時間のデスクワークやスマートフォンの使用による首への負担などが挙げられます。首への負担は、首がまっすぐになってしまうストレートネックの状態を招き、頚椎椎間板ヘルニアのリスクを高めてしまうので注意が必要です。
症状は圧迫される神経の種類によって異なります。脊髄が圧迫されると、手足のしびれ、手先の細かい動作の困難さ、歩行障害、排尿・排便障害などが現れることがあります。また神経根が圧迫されると、片側の腕や指に強い痛みやしびれが生じ、力が入りづらくなることがあります。これらの症状は、首を後ろに反らすと強く現れる傾向にあります。
診療に当たっては、まず医師が問診や診察を行い、首の動きや神経の反応を確認します。その後、X線やCT、 MRIなどの画像検査で、骨の状態や椎間板の突出と神経の圧迫状態を確認し、治療法を検討します。症状が軽い場合は、保存療法を行っていきます。
保存療法では、まず首を安静にすることが重要で、頚椎カラーという装具を装着します。また、痛みやしびれに関しては、鎮痛剤や湿布などの薬物療法で症状を和らげます。さらに、首周りのマッサージ、運動療法、温熱療法、牽引療法といった理学療法で症状の改善を図っていきます。歩行や軽い運動は積極的に行うようにし、長時間寝たきりにならないようにすることが重要となります。
頚椎椎間板ヘルニアは、多くの場合、安静にし、薬物療法を行うことで症状が改善しますが、痛みが悪化する場合、力が入りにくくなった場合、排尿・排便に問題が出た場合は、速やかに手術することが検討されます。手術には頚椎前方除圧固定術や頚椎椎弓形成術などがあります。手術が必要となった場合は、連携する医療機関をご紹介いたします。
後縦靱帯骨化症
後縦靭帯骨化症は、背骨の中を縦に走り、椎骨を後縁で上下に連結する後縦靭帯と呼ばれる組織が、骨のように硬くなってしまう病気です。それにより背骨の中を通る脊柱管という神経の通り道が狭くなり、脊髄や神経根を圧迫することで、手足のしびれや痛み、運動障害など様々な神経症状が引き起こされます。後縦靭帯骨化症は指定難病の一つに指定されています。
後縦靭帯骨化症は、頚椎、胸椎、腰椎のいずれにも起こりますが、最も多くみられるのが頚椎です。50歳前後で発症することが多く、男性に多い傾向があります。 また糖尿病の患者さまに多くみられることも分かっています。原因はまだよくわかっていませんが、遺伝的要因、性ホルモンの異常、カルシウムやビタミンDの代謝異常、糖尿病、肥満などが複合的に関係していると考えられています。とくに家族内発症が多いことから、遺伝子の関連が注目されています。
症状は骨化が起こる部位によって異なります。頸椎に発症した場合は、首や肩甲骨周辺の痛み、指先のしびれなどが初期症状として現れます。ボタンがうまくはめられない、箸でものがつかめないなど巧緻運動障害を起こすことがあり、進行すると歩行障害や排尿・排便障害が現れる場合もあります。胸椎では、体幹や下半身のしびれや脱力などの症状が現れます。また腰椎では足のしびれや痛みなどが現れます。ただし後縦靭帯骨化症は、症状がないまま経過することもあります。
後縦靭帯硬化症の治療としては、軽度の場合は、消炎鎮痛剤や神経障害性疼痛治療薬などによる薬物療法や、頚椎カラー等による装具療法で経過観察します。ただし日常生活に支障が出るほどの症状がある場合、手術が必要になることもあります。後縦靭帯骨化症は再発することもあるため、手術後も定期的な検査が必要となります。予防法は確立していませんが、肥満や糖尿病などの生活習慣病の予防や、正しい姿勢を心がけることが重要だと考えられています。
黄色靱帯骨化症
黄色靭帯は、背骨の後方にある椎弓と呼ばれる骨と骨の間を繋ぐ靭帯で、脊髄神経の後ろ側に位置しており、背骨を安定させています。黄色靭帯骨化症は、この靭帯が骨のように硬くなる病気です。厚みも増すことで、脊髄神経が圧迫され、様々な神経症状を引き起こします。主に背中の下部から腰にかけて発症することが多く、足のしびれや痛み、歩行困難などの症状が現れます。
40歳以上の患者さまが多く、男女差はありません。 はっきりとした原因は分かっていませんが、遺伝や加齢、外から何らかの力がかかることなどが関係していると考えられています。黄色靭帯骨化症は、国の指定する特定疾患(難病)の一つに指定されており、医療費助成制度が利用できる場合があります。
黄色靭帯骨化症では、骨化してくる部位が胸椎に多く、そのため症状としてはしびれや痛みなどが足に出ることが比較的多くなっています。ただし、頸椎で起こることもあり、進行すると、歩行が困難になったり、排尿障害(頻尿、尿漏れなど)が現れたりする場合もあります。また、少し歩くと痛みやしびれで歩けなくなり、休むと再び歩けるようになる、間欠性跛行という状態が引き起こされることもあります。
診療にあたっては、X線検査やCT検査、MRI検査などの画像検査を行い、黄色靭帯の骨化の有無や程度、神経への圧迫の程度などを確認します。その結果、症状が軽い場合は、安静にし、消炎鎮痛剤や神経障害性疼痛治療薬、ビタミンB剤などによる薬物療法や、リハビリテーション等を行います。神経の麻痺が進行している場合は、神経を圧迫している骨化した靭帯を取り除く手術を検討します。
外傷性頚部症候群
外傷性頚部症候群とは、交通事故などによって首に強い力が加わり、首の周りの筋肉や靭帯などの組織が損傷することで起こる症状のことです。 一般的には「むち打ち」と呼ばれることが多いものです。X線検査やMRI検査では、骨折や脱臼などの異常は見られず、診断は主に症状や事故の状況などから総合的に判断されます。
事故にあったときに、反射的に首を守る防御のための筋緊張が生じ、衝撃の大きさによっては筋の部分断裂や靭帯の損傷が生じている場合があります。症状は様々で、首の痛みだけでなく、頭痛、肩こり、めまい、吐き気、しびれ、耳鳴り、視覚障害、疲労感、集中力の低下、睡眠障害などが現れることがあります。これらの症状は、事故直後から現れることもあれば、数時間後や数日後に現れる場合もあります。
治療の基本は、頚椎カラーを装着し、首を安静に保つものです。併せて痛みなどの症状に対しては、消炎鎮痛剤などによる薬物療法を行います。外傷性頚部症候群は、多くの場合、自然に治癒しますが、適切な治療を行わないと症状が長引いたり、慢性化したりすることがあります。そのため、早期に適切な治療を受けることが重要です。
症状が長引く場合には、理学療法や運動療法などのリハビリテーションが有効なこともあります。骨折などの明らかな異常がないにもかかわらず、長期間にわたって頚椎カラーを装着すると、かえって首の痛みが長引く原因となることがあるので注意が必要です。
頚椎症
頚椎症とは、加齢に伴い首の骨(頚椎)と、骨と骨の間にあってクッションの役割を果たす椎間板が変形し、神経を圧迫することで様々な症状が現れる病気です。主な原因は10代後半から始まると言われる椎間板の老化です。そのため、中年以降に多くみられるものとなっています。
加齢により椎間板の水分が失われ弾力性が低下することで、椎間板が潰れたり膨隆したりします。さらに椎間板が付着している頚椎の縁も一緒に押し広げられ、骨棘と呼ばれる骨のとげが形成されることもあります。これらの変化によって脊柱管(神経の通り道)や椎間孔(神経の枝が通る孔)が狭くなり、神経が圧迫され、症状が現れます。頚椎症は、神経が圧迫される部位によって、主に「頚椎症性脊髄症」と「頚椎症性神経根症」の2つに分けられます。
「頚椎症性脊髄症」では、脊髄が圧迫されることで、手足のしびれや動かしにくさ、歩行障害などが現れます。進行すると排尿・排便障害が起こる場合もあります。転倒などの軽い衝撃でも症状が悪化する可能性があるため、注意が必要です。
「頚椎症性神経根症」では、脊髄から枝分かれした神経根が圧迫されることにより、首や肩のこり、腕や手のしびれや痛みなどの症状が現れます。痛みが腕や肩甲骨にまで広がり、手に力が入りにくくなる場合もあります。一般的に、首を後ろに反らせると痛みが強くなります。
診断にあたっては、骨の状態を確認するX線検査や、椎間板や神経の状態を詳しく調べるためのMRI検査を行います。治療としては多くの場合、薬物療法や装具療法などの保存的治療が行われます。薬物療法では、痛みやしびれに対し、消炎鎮痛剤や神経の働きを助ける薬などを服用します。装具療法では、首を固定する頚椎カラーを装着するなどします。保存的治療で効果がない場合は、「前方固定術」や「椎弓形成術」といった手術を検討します。
頚椎症は加齢が主な原因のため、予防は難しいものとなっています。転倒などで頚に負担をかけないことが大切です。また頚椎症は放置すると症状が悪化する可能性があるため、気になる症状がある場合は、お早めにご受診ください。
肩の症状について

投球障害肩(野球肩)
投球障害肩はボールなどを投げる動作を繰り返すことで肩に痛みや機能障害が生じる症状の総称です。野球をする方に多くみられることから、野球肩と呼ばれることもあります。野球のほかには、ソフトボールやハンドボール、さらには水泳など、腕を上げて行うスポーツで多くみられます。
投球動作は、体幹や下半身で生み出されたエネルギーを腕に伝え、ボールを高速で投射する複雑な動きです。この一連の動作の中で、肩関節には大きな負担がかかり、繰り返し行うことで肩関節の構成組織に損傷が生じることがあります。とくに投球動作の加速期には肩関節に強い圧力がかかるため、腱板や関節唇が骨と骨の間に挟まれる「インターナルインピンジメント」という状態が起こりやすくなります。
また減速期には、腕が遠心力で引っ張られ、肩の後方の筋群や関節唇に負担がかかります。
これらの負担が積み重なることで、腱板損傷、関節唇損傷、インピンジメント症候群などの障害が発生し、痛みが生じます。成長期のお子さまでは、上腕骨の成長軟骨が損傷され、「リトルリーグショルダー」と呼ばれる障害を引き起こすこともあります。
投球障害肩の治療は、基本的には保存療法が中心となります。まずは障害を引き起こす原因となっている投球動作を中止し、肩関節を安静にさせます。期間は3~4週間が目安です。マッサージやアイシングも有効な場合があります。
痛みが強い場合は、湿布や痛み止めの使用や、肩関節の固定を行うこともあります。痛みが軽減してきたら、肩関節の柔軟性回復のためのストレッチ、肩甲骨の安定性を高めるための腱板訓練、肩関節周囲の筋力トレーニングなどを行います。野球の場合、投球フォームの改善も重要です。
保存療法で改善が見られない場合や、関節唇損傷によるひっかかり、重度の腱板損傷がある場合は、手術を検討します。手術は関節鏡を用いて行われ、損傷部位の修復などが行われます。いずれの場合も、治療後にはリハビリテーションを行うことが重要です。
投球障害肩は、早期に治療を開始することが重要です。 肩に違和感や痛みを覚えたら、我慢せずに早めにご受診ください。
五十肩
肩腱板断裂
肩腱板は、4つの筋肉や腱によって構成され、肩甲骨と上腕骨の間に位置し、肩関節の安定化やスムーズな動きをサポートする役割を担っています。この肩鍵板が損傷・断裂した状態が肩鍵板断裂です。肩腱板断裂の原因は、加齢による腱板の変性、腱板に負担をかける反復動作、外傷などです。 とくに野球、水泳、テニスなど肩を酷使するスポーツや、重い物を持ち上げる動作を頻繁に行う人は注意が必要です。
主な症状は、肩の痛みや動かしにくさです。腕を上げるときに痛みを感じたり、夜間や安静時にズキズキとした痛みが生じたりすることがあります。 また、腕に力が入りにくい、腕を上げた状態で維持するのが困難、といった症状が現れることもあります。
似た症状を呈するものに「五十肩」がありますが、違う部分としては、肩腱板断裂では「痛いが何とか腕が上がる」のに対し、五十肩では「痛いしどうやっても腕が上がらない」ことが多いという特徴があります。ただし五十肩は多くの場合、自然治癒することが望めます。
肩腱板断裂の治療は断裂の程度や症状によって異なります。X線検査やMRI検査を行い、肩関節の状態や腱板の状態を確認します。保存療法が選択された場合は、痛み止めや炎症を抑える薬の服用、肩関節内の動きを滑らかにするヒアルロン酸注射、肩関節周囲の筋肉の柔軟性や筋力を改善するリハビリテーションなどが行われます。腱板断裂は自然に治癒することはありませんが、保存療法によって日常生活に支障がないレベルまで回復することが期待できます。
保存療法で効果が見られない場合や、断裂の程度が大きい場合には、手術が必要となることもあります。手術には、関節鏡手術と通常手術があり、どちらの方法が適しているかは、損傷の程度や医師の判断によって決定されます。
石灰沈着性腱板炎
石灰沈着性腱板炎とは、筋肉や腱からなり、肩関節を支える肩の腱板に、リン酸カルシウム結晶(石灰)が沈着し、痛みや運動制限を引き起こす病気です。40~50代の女性に多くみられ、夜間に突然発生する激しい肩の痛みが特徴です。痛みで眠れないこともあり、肩関節を動かすことも困難になります。症状は1~4週間、激痛などの強い症状がみられる急性型のものもあれば、半年以上、運動時の痛みなどが続く慢性型のものもあります。
石灰沈着性腱板炎では、腱板に付着したミルク状のリン酸カルシウム結晶が、時間と共に固まって硬くなり、蓄積していくことで、痛みなどの症状が現れると考えられています。その原因はまだよくわかっていませんが、肩を使う労働やスポーツなどとの関連性は認められておらず、使い過ぎが直接の原因となるわけではないと考えられています。その一方、糖尿病や甲状腺機能障害などの内分泌疾患との関連性が指摘されています。
五十肩も同じような症状で、同じような年代にみられることが多くなっていますが、五十肩は関節包やその下にある滑液包に炎症が起こる病気であり、肩石灰沈着性腱炎のように、肩腱板内の石灰沈着はみられません。
治療にあたっては、肩関節の動きなどを医師が確認し、X線検査で腱板部分の石灰沈着の有無を確認します。また石灰沈着の位置や大きさを詳しく調べるために、CT検査や超音波検査が行われることもあります。
石灰沈着性腱板炎は多くの場合、保存治療で症状は改善します。三角巾などで肩を固定し安静にして、非ステロイド性消炎鎮痛剤の内服薬などを用います。痛みが強い場合は、水溶性副腎皮質ホルモンと局所麻酔薬を滑液包内に注射するという治療を行う場合があります。
このほか、発症初期は石灰がクリーム状で柔らかいため、針を刺して吸い取るという治療や、対外衝撃波で石灰を砕き、吸収を促進するといった治療法もあります。保存療法で症状が改善しない場合は、石灰沈着を摘出する手術を検討します。手術は関節鏡と呼ばれる内視鏡を用いて行われることが多くなっています。
肩関節脱臼
肩関節脱臼は腕の骨(上腕骨)が肩甲骨から外れてしまうケガを指します。肩は人の体の中では最も広範囲の動きを求められる関節です。そのため受け皿となる肩甲骨の関節窩(肩甲骨のくぼみ)の構造が浅くなっており、脱臼もしやすくなっています。主な関節脱臼の50%は肩関節脱臼であるというデータもあります。
肩関節脱臼は、スポーツや転倒など、肩に大きな力が加わった時に起こりやすく、とくにラグビーや柔道などのコンタクトスポーツや、転倒のリスクが高いスポーツで多く見られます。交通事故によって引き起こされることもあり、年齢層としては若い男性と高齢女性に多く発症する傾向があります。
肩関節脱臼によって引き起こされる症状としては、強い痛み、そして肩を動かせなくなることがあります。肩の丸みが失われる、肩甲骨の外側の出っ張りが目立つようになる、といった場合もあります。また肩は不安定な骨形態の分、関節を覆う関節包や靭帯、周囲の筋肉などの軟部組織による安定性が保たれているため、脱臼に伴って周囲の靭帯や腱、神経などにも損傷を与える可能性があり、それによる痛みやしびれなどの症状が出ることもあります。
診断ではX線検査やCT検査を行い、肩甲骨と上腕骨の位置関係を確認して、脱臼の状態や骨折の有無などを確認します。肩関節脱臼の治療では、まず外れた関節を元に戻す「整復」を行います。整復は腕を引っ張る、肩を外にひねるなど、様々な方法があります。整復後は固定して安静にし、損傷した組織が修復されるのを待ちます。目安としては3~4週間です。
若いころに脱臼をすると、再発する可能性が高いと言わりており、脱臼を繰り返す「反復性肩関節脱臼」といわれる状態になることがあります。その場合、再発予防の手術を検討する場合があります。
肩関節脱臼は適切な治療を行えば、多くの場合スポーツ復帰も可能な怪我です。しかし、再脱臼のリスクも高いため、予防や適切なリハビリテーションが重要です。また脱臼は無理に自分で元に戻そうとすると、骨折を生じる危険があります。脱臼した際には速やかにご受診ください。
変形性肩関節症
肩の関節は肩甲骨と上腕骨という骨で構成されていますが、これらの骨の表面は、軟骨で覆われています。この軟骨がすり減って肩の骨が変形してしまうのが、変形性肩関節症です。
軟骨はクッションのような役割をしていて、肩関節をスムーズに動かすために重要なものです。ただ加齢や過剰な負荷などによって軟骨がすり減ると、炎症が起こったり、骨棘という骨の突起が発生したりします。それにより、肩の痛みや腫れ、可動域の制限などの症状が引き起こされます。痛みは肩を動かしたときに強くなることが一般的ですが、安静時や夜間に痛みを感じることもあります。
変形性肩関節症の原因は、大きく分けて明らかな原因がない一次性と、原因が判明している二次性に分けられます。 一次性は、骨格の問題や肩関節への過負荷などが考えられますが、はっきりとした原因は分かっていません。 一方で、二次性は、腱板断裂や上腕骨頭壊死、関節リウマチなどが原因で起こります。 とくに腱板断裂は加齢に伴い増加しており、変形性肩関節症の大きな原因となっています。
治療は、保存的治療と手術的治療の二つに分けられます。変形性肩関節症は進行性の病気であるため、早期に発見し、適切な治療を開始することが重要です。
痛みが軽い場合は、薬物療法やリハビリテーションなどの保存的治療を行います。具体的には、痛み止めや炎症を抑える薬(非ステロイド性抗炎症剤)を内服したり、湿布を使用したりします。また、関節内にヒアルロン酸やステロイドを注射することもあります。さらに、肩関節の動きを改善するための運動療法も行います。
保存的治療で効果がない場合や、日常生活に支障が出るほどの痛みがある場合は、手術が検討されます。手術には、人工関節置換術などがあります。人工関節置換術とは、すり減ってしまった軟骨や骨の一部を人工物に置き換える手術です。
変形性肩関節症は進行性の病気であるため、早期に発見し、適切な治療を開始することが重要です。
上腕二頭筋長頭腱炎
上腕二頭筋は肩から肘にかけて走る筋肉で、いわゆる「力こぶ」を作る筋肉です。この筋肉の肩側にある長頭腱という部分に炎症を起こして痛みなどの症状が現れるのが上腕二頭筋長頭腱炎です。
肩や肘の動きに重要な役割を果たしている長頭腱は、上腕骨の結節間溝という溝の中を通っています。しかし、この溝の中は狭いため、摩擦が起こりやすく、炎症を起こしやすい場所でもあります。とくにスポーツや仕事などで腕を酷使すると、腱への負担は蓄積し、発症しやすくなります。
主な症状としては、肩の前から二の腕にかけての痛みで、肘を伸ばしたまま物を持つ時や、後ろに手を回す時に痛みを感じることがあります。また夜間や安静時にも痛みが出ることもあります。また上腕二頭筋長頭腱が断裂してしまうと、腕に力が入りにくくなります。
野球、テニス、バレーボール、水泳などのオーバーヘッドスポーツで起こりやすい傾向にあり、加齢による腱の弾力性や耐久性の低下や、肩関節の障害による肩関節の不安定性も上腕二頭筋長頭腱炎を招く原因となります。また事故などによる外傷によっても引き起こされることがあります。
治療は保存療法を基本に行われます。薬物療法として非ステロイド性抗炎症薬の服用やステロイドの注射などを行います、物理療法としては温熱療法や冷却療法など、痛みの軽減と血行促進を目的とした治療を行います。さらに運動療法を行い、筋力強化や可動域改善を図っていきます。保存療法で症状が改善されない場合は、手術を検討します、手術の種類としては、上腕二頭筋腱切離術や上腕二頭筋腱固定術といったものがあります。
上腕二頭筋長頭腱炎を予防するためには、過度なスポーツや労働を避け、適切な休息をとることが重要で、運動前後のウォーミングアップとクールダウンをしっかり行うことも大切です。上腕二頭筋長頭腱炎は、放置すると日常生活に支障をきたす可能性があります。早期に適切な治療を行うことが大切です。
